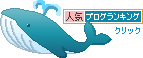「夜のななふし-03(3)」楢﨑古都
夜のななふし-03(3)|楢﨑古都 @kujiranoutauuta #note #熟成下書き https://t.co/Ij8AG3asoH
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2020年1月2日
ハルキを幼稚園へ送ると、私にはすることがなくなってしまう。バイトをする気にもならないし、金なら親父の不動産から毎月自動的に振り込まれてくる。
親父がいる部屋に戻る気はしなかった。かといって他に行くあてがあるわけでもない。電車に乗って歓楽街まで出てゆく気力もなかった。さしたる目的もなく、私は高校行きのバスに乗っていた。
駅とは逆方面へ向かうバスは、まだ遅い朝の通勤時ということもあって、まばらに人がつり革を握って立っていた。しばらくして空いた、センターライン側の席に腰を下ろす。みだれてしわくちゃになったセーラー服のプリーツを、両手で気持ち押さえつけながら座った。
視線を窓の外に投げ、気だるくバスに揺られた。信号待ちで停車しエンジンが切られると、少し効きすぎた暖房が車内にこもった。眺めていた右手の窓辺から、反対側の窓外に視線を変える。通路に立つ人たちの隙間をぬって、私は路地と人影に視線を取られた。車一台がやっと通れるくらいの狭い路地だった。三個の人影が、横たわるくたびれた猫を囲み覗き込んでいた。
しゃがみこんでいる中年女は、パーマのとれかかった髪を何度も耳にかける仕草をしながら猫の頭をなでていた。男が二人、女の後ろから様子を眺めている。白い寝巻き姿のまま表へ出てきてしまった寝癖の老人と、日がな散歩をして過ごしていそうな中年男だった。大の大人が三人も、薄汚れた一匹の猫を囲んでいる光景はいささか異様なものに映った。
猫は人に慣れているのか、なでられてもまったく微動だにしない。四肢を投げ出し、腹を見せて女のなすがままにまかせていた。男たちは揃って腕組みし、つっ立っている。
女が、赤ん坊の頭を持ち上げるときの要領で頭をそっと持ち上げたときも、猫はまったく動かなかった。ただ、見開かれた両眼が低い太陽に反射して金にも緑にもゆらいで見えただけだ。何ものも、それは見てはいなかった。女の手が猫の瞼を閉じる。待っていたかのように再びエンジンがかかり、バスは視線を引きずりながら走り出した。
目をつむり眠ろうとしても無理だった。まばたきするたび、瞼の裏に猫の姿がよみがえった。女の手に支えられた頭には重さがなかった。嫌なものを見てしまった、という後味の悪さはなかったが、心許ない不安定な所在なさは腕や足に滞っていた。効きすぎた暖房が疎ましく思えてきて、私はバスを降りた。
足が自然とさっきの路地へ向いた。ポケットから煙草を取り出し火をつける。かかとを削りながら歩いた。口元にあてた中指と人差し指を細めた目で追うと、北風に吹かれて煙が顔にかかった。
猫も人影もすでに路地にはなかった。冬の太陽が乾燥したアスファルトに弱い陽光を落とすばかりだった。ブロック塀の向こう側から、かすかに人の気配とテレビの音がする。猫に出会えなかった落胆よりも、安堵の方が大きかった。
ベルの音がして道をあけると、前と後ろとに幼い子どもを乗せた母親の自転車が走り抜けていった。無造作にひとつに束ねられた髪の毛が、子どもと一緒に揺れている。煙草を靴のかかとでもみ消して、両手をポケットにしまった。
路地を出て、私は陸橋を見つける。嬉々としてそれに向かい、登っていった。制服が汚れるのも気にせず、柵に足をかけ身を乗り出していた。腕や足に滞るものを、下から吹き付ける冷たい風で拭いたかった。車の走列に次から次へと自分を重ね合わせ、猫は轢かれて死んだのだろうかと考える。見下ろしていた顔を上げると、冬の晴天が高く広がっていた。
排気ガスの混じった冷気を胸いっぱいに吸い込み、勢いつけて柵から飛び退く。意味もなく笑い出しそうになるのをこらえて、階段を一段抜かしで下りていった。なぜハルキがジャングルジムに登りたがるのか、少し分かった気がした。
「夜のななふし-03(2)」楢﨑古都
夜のななふし-03(2)|楢﨑古都 @kujiranoutauuta #note #熟成下書き https://t.co/deUEt3e4AQ
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2020年1月2日
飲むの、と胸元にコーンスープを差し出したら、口を開けて頷いた。熱い缶を膝の上にのせ、袖口を手のひらまで引っ張り上げて両手で持つ。プルトップが開けられず、先に開けたもう一本を手渡してやると、吹く風に赤く染まった頬が控えめにゆるんだ。少しずつ飲んだコーンスープはかじかんだ手のひらを熱くし、食道を通って胃の中をじんわりと温めた。
ちらちらとこちらをうかがって行く通勤者たちを横目に、私たちは食事をすませる。食べ終わった幼稚園児に促されて、立ち上がった。
握りしめられた片手は握り返さない。でも歩調は、歩幅の狭いハルキと合わせている。私一人ならば十分程度の道のりを、倍の時間かかって幼稚園まで歩く。私がハルキに歩調を合わせるのはこのときだけだ。時間通りにハルキを幼稚園へ送って行って、園児たちの母親に出くわしてしまうのが面倒だった。
私はわざとハルキを遅刻させる。だから新米の幼稚園教諭は今日も私に小言を言う。
「黒田さん、集合は八時半だっていつも言ってるでしょう。ちゃんと時間は守ってください。」
幼稚園教諭の職業病なのか何なのか知らないが、彼女の喋り方は誰に対しても子ども相手のときと基本的に変わらず、聞いていてとても疲れる。すみません、と頭を下げてみせたりしながらも、私はその喋り方にいつも閉口してしまう。ひらがなの音でばかり発音するから、声のトーンにしまりがないのだ。
「あなたも学校があるから大変なのはわかるけど。でもこの時間じゃ、あなただって学校に遅れてしまうんじゃないの。」
どうせ行ってないんでしょう、という蔑みが目に浮かんでいた。しわくちゃのセーラー服を無遠慮にねめつけ、わざとらしく彼女はため息を吐く。ハルキの服装までは、もう呆れてか注意もしなくなった。水色のスモッグはところどころ食べ物の染みがついてくすみ、膝丈半ズボンの下でたるんだ靴下はちぐはぐだった。
せんせい、と下駄箱から数人の甲高い声が彼女を呼ぶ。はぁい、と返事をして、みんなお教室で待っててね、と笑顔が諭す。いい子ぶりを見せつけたい一心の園児たちは、素直に返事して駆けて行く。
園児たちの溌剌さはハルキには無縁のものだ。うまく喋れないのに加えて、背格好も同年代の子どもたちに比べてひとまわりは小さい。来年小学校へ入学しても、集団の中ではたしてうまく立ち回れるかどうかは疑問だ。もしかして、ランドセルの重みでひっくり返ったりするんじゃなかろうか。そうしたら、私は思いっきり笑ってやる。
「それじゃ、おあずかりします。」
私の元から離れたハルキは幼稚園教諭に手を取られる。まるで物みたいな言い方だ、と思った。目は見ずに、お願いします、と形式的に頭を下げて、私はハルキに背を向ける。
ハルキはきっと、私の姿が見えなくなるまでそこで私の背中を追っている。やがて少し強く手を引かれて教室に入るが、しばらくは窓の外ばかり気にして名前を呼ばれても振り向かないだろう。子どもの熱い体温で握りしめられていた左手が、指の感触を覚えていた。
ソナチネのような毎日でしたもう二度とふり返らない、さよなら(楢﨑古都)

閉めきりの部屋で過ごした二年間 隙間のきざし遠かつた朝
したためる所作も忘れた果たし状または恋文どれもゴシック
ソナチネのような毎日でしたもう二度とふり返らない、さよなら
転職祝いに岩手申し込んだ📚 https://t.co/pyHSsXYQMp
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2020年1月17日
額縁に縫いとめられし少女たち囀りまでも時をこえゆく(楢﨑古都)

ひとしきりあなた想つて泣いたので小さな海を漕ぎだしてゆく
額縁に縫いとめられし少女たち囀りまでも時をこえゆく
胸のうち告げられずいま思い出は三十一文字のリズムとなつて
額縁に縫いとめられし少女たち囀りまでも時をこえゆく
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2020年1月12日
『 少 』 楢﨑古都 #うたの日 #tanka
・・・#ルノワール展 #横浜美術館#ピアノを弾く少女たち
・・・https://t.co/pFJISekcTM
「夜のななふし-03(1)」楢﨑古都
夜のななふし-03(1)|楢﨑古都 @kujiranoutauuta #note #熟成下書き https://t.co/89H95OZO04
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2019年12月31日
ハルキは律儀に幼稚園へ通う。今朝も、昨日遅くまで起きていたくせに自分から起き出して私を揺すり起こした。暖房をかけっぱなしで寝た室内は充分過ぎるほど温もり、喉をひどく渇かせた。
二度寝しようとする私を再度揺すり起こし、起き上がったのを確認してからハルキは着がえはじめる。たんすにしまわれず床に散乱している服の中から、下着やら靴下やらを適当に選び出して身につける。私は壁にかかったしわくちゃのセーラー服に袖を通した。高校へ行くためではない。ハルキを幼稚園へ送っていくために、私は毎朝このセーラー服を着る。制服を着ていたほうが、朝の喧騒には紛れ込みやすいのだ。不機嫌な顔を見せれば、あえて話しかけてくるやつらもいなくなる。
髪をとかして、ハルキに通園かばんを背負わせると、時計の針は七時を十分ほど過ぎたところだった。床に脱ぎっぱなしにしていたコートを拾い上げ、二着分を腕に持つ。安っぽくて、だからわざといつも着ている量販店のコートは暖かい。
廊下に出ると、空気の冷たさが暖房でほてった身体に寒さを思い出させた。リビングにはまだ酒のにおいが充満していた。水が飲みたくて、台所の蛇口をひねる。水の冷たさは乾燥しほてった両手にも同じ感覚を蘇らせた。
カウンターキッチンから見える親父は、いつの間に移動したのかソファの上でだらしなく眠りこけている。相変わらず耳障りないびきは絶えない。その様を見ていたら、再び無性にこの男を蹴り飛ばしたい衝動に駆られた。けれども、強情に私のプリーツスカートを引っ張る細腕が、私からその機会を奪った。コートを羽織り、私たちは玄関の鍵を閉めずに家を出る。
朝ご飯を買いにコンビニへ寄り、公園で包みを開いた。ハムタマゴサンドと、かにパンと、二百ミリリットルパックの牛乳を二本。相当喉が渇いていたのか、ハルキは喉を鳴らして牛乳を一気に飲み干した。続いてかにパンに手をのばし、頬を膨らませ口の中をいっぱいにする。飲み込む音が聞こえてきそうだ。私はタマゴサンドから口につけ、口休めにストローで牛乳を吸う。冷たい牛乳は思いのほか早く身体を冷やしていく。
ハルキをベンチに残して、公園脇の自販機へ立った。飲み物の中からコーンスープを選んで二回ボタンを押す。ついでに隣の自販機からピースという名の煙草も落とす。
コーンスープはコートのポケットにしまって、百円ライターを取り出した。火は乾燥した空気によって威勢のよい音を立て、買ったばかりの煙草の先端を瞬時に燃やした。ベンチへ戻るまでに三口吸って、腰かけると同時に長いため息をつく。ハルキの顔の前で長い煙を吐いた。煙にむせかえる姿を見て、私はとても満足する。ハルキは決して文句を言わない。私がベンチに戻ってくるまでの間、こいつはずっと視線を私から逸らさずにいたのだろう。
「夜のななふし-02(2)」楢﨑古都
夜のななふし-02(2)|楢﨑古都 @kujiranoutauuta #note #熟成下書き https://t.co/xtaq61E21j
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2019年12月31日
エレベーターで降りていくときから私の腕にしがみついていたハルキは、公園へたどりつくとようやくその手を離した。つまらせた鼻を音を立ててすすり、私の顔を仰ぎ見る。水色のスモッグは、セーターの上から重ね着されているにも関わらずまったく着膨れしていなかった。まるで寸胴の袋をかぶせただけみたいな格好に見える。あごで、行っていいと指し示すと、ハルキはジャングルジムの方へ駆けて行った。
細っこくて危なっかしい手足でジャングルジムによじ登っていくハルキに、ふと無性に腹が立った。どうしてあいつは、あんなにもう楽しそうに遊んでいるのだ。どうせ登ったって、てっぺんまで到達できるわけでもないくせに。木製のベンチに腰かけ、私は煙草を吸うという行為のために火をつける。保護者を気取った妙なプライドで半分演技がかった吸い方をしたら、一口目で大げさにむせた。ハルキが何事かと驚いてこちらを振り返るのが分かったが、私はすまして二口目を吸い込んだ。そして吐き出す。ベンチの背もたれにはりついたななふしが、じっとこちらを見ていた。
親父から逃げ出したところで、私たちにあてなどなかった。結局またあの部屋へと帰るしかないことを、ハルキも知っている。だからなのか、ハルキは舟をこぎはじめてもなお遊びつづける。大体いつもそのくらいが潮時で、私は眠りに落ちる寸前の幼児の手を引いて帰るのだ。絶対に、抱き上げてやったりなんかしてやらない。
掴んだ手は寒さに冷え切っていた。頭が支えを失って落ちては起き上がり、落ちては起き上がりを繰り返した。手を離したら、その場に崩れ眠りこんでしまうだろう。やっとエレベーターに乗り、壁面に肩を預けた。ハルキは二の腕を私に支えられぶら下がっている。玄関まで何とか歩かせて、物音がしないのを確かめてから鍵を回した。
リビングのドアを開けると、暖かい空気とともに一斉に酒の匂いが身体を包んだ。窓から入ってくるわずかな明かりで、親父がソファの横にのびているのが見える。カーテンは開けられたままだ。ひどく耳障りないびきだけが、静まり返った室内で不規則な呼吸をつづけている。
私はリビングを抜けた自分の部屋にハルキを先に連れていき、スモッグとズボンと靴下だけ脱がせて布団にもぐりこませた。リビングへ戻って暖房を切る。カーテンを閉めて、暗闇の中部屋まで戻ろうとしたとき、足が親父の身体に躓いた。起こしてしまう、と慌てる一方で、この男の肩口を心底蹴飛ばしてやりたい、と思った。でもすぐに気持ちは萎えてしまう。自分の足指の先が、ほんの少しでもこの男の体に触れてしまうことの方が、鳥肌が立った。
暗闇に慣れた目を凝らして部屋へ戻った。鍵を閉めて、自分もベッドに入る。隣でかすかに寝息をたてている小さな身体に触れてみると、ほのかに温かかった。
「夜のななふし-02(1)」楢﨑古都
夜のななふし-02(1)|楢﨑古都 @kujiranoutauuta #note #熟成下書き https://t.co/3sS0PUso6d
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2019年12月29日
「ユキちゃ、」
意志の弱いおびえたような声で、遠慮がちに私の名前を呼ぶハルキのことが、私は心の底から気に食わない。読んでいた雑誌をソファの足元へ放り、携帯電話の液晶画面に視線を落とす。わざとONにしたボタンの確認音が邪魔だった。
「ユキちゃん、」
「ちゃん付けで呼ぶな。」
あ、と声を漏らして口ごもり、目だけせわしなく動かして何か言いたそうな視線を投げかけてくる。言葉が遅れている、と思う。
「あの、」
「うるさいな、なに。」
にらみつけると、下を向いて目をそらした。肩からななめにさげた通園かばんに両手を突っ込んで、さっきから何やらごそごそと中身をいじくっている。
パステルイエローの通園かばんは、やせたハルキの身体には不釣合いだった。水色の帽子とスモッグも、その体格をいっそう貧相に見せている。幼稚園から帰って来たきり、今日はいつまでも服を着がえようとしない。
いったい何を出ししぶっているのか、通園かばんのひもを半ば強引に引っぱったとき、何の前触れもなく玄関のドアノブを無理やり回し、こじ開けようとする音が響いた
親父だ。ドアノブが大きな音を立ててひねくり回されている。こちら側から鍵を開けてやるまで、酔って帰って来たときの親父はいつもこうなのだ。ハルキの肩がびくりと震える。私は通園かばんから手を離して玄関へ向かった。ハルキは納戸へ逃げ込む。
酔った親父の馬鹿力に対抗して、一度ドアを正位置に戻してからどうにか鍵を外してやる。同時にドアは勢いよく開いた。土足で家の中へと踏み込んでくる。足音が家中を歩き回る。
階下の住人は先月引っ越して行ってしまった。気の弱い老夫婦は私たちに優しかった。自分たちだけでは食べ切れないからと、多めに作った煮物や炊き込みごはんなんかをよく分けてくれた。しかし、いつも予告なしに降ってくる騒音に耐えかねていた。このマンションは親父の不動産だから、所有者に向かって出て行けとも言えない。随分と良くしてもらっていたのに、もう二度と会うこともないのだろう。
「水持ってこい。」
廊下から様子を窺っていた私を血走った目でにらみつけると、親父はソファに腰を降ろした。台所でシンクにおかれたままのコップに水道水を注ぎ入れ、ソファ前のローテーブルにわざと音を立てて置く。
「なんだその態度は。」
伸びてくる腕を後ろに遠退いてかわし、その場を離れようとすると頭ごなしに怒鳴られた。
「それが親に対する態度か。その目は何だ。何も出来ない子どものくせに、態度ばっかりいっちょ前にでかくなりやがって。何様のつもりだ?」
赤みを増した親父の顔を、私は心底醜いと思う。まだ五時過ぎだというのに、いったいどこでこんなになるまで飲んできたのだ。適当な女でも買って、帰ってなど来なければよいものを。
「おまえには口がないのか。おい、返事をしろ。」
水を一気に飲み干すと、親父はさらに大きな音を立ててコップをテーブルに打ち付けた。私は台所の床下からウィスキーを取り出し、無言で親父の前に差し出す。たるんだ顔の筋肉がゆるみ、親父は引きつった笑みをうかべた。一口舐めると思い出したように立ち上がり、トイレに入った。そのすきに私は廊下の納戸へと向かう。戸を開けた瞬間、ハルキはひいっと息を飲んで後ずさった。小刻みに震える身体を引きずり出し、強引に手首を掴んだ。足がもつれて転びそうになると、掴んだ手首を持ち上げた。靴を履かせ立ち上がり、音を立てずに玄関を出る。枯れ枝みたいに細っこい指が、私の服の裾をにぎりしめた。一歩外へ出ると、途端に鳥肌が立った。けれど、上着まではおっている余裕はなかった。吐く息が白く溜まって、頬がしびれた。
今週のお題「二十歳」