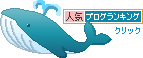「夜のななふし-03(3)」楢﨑古都
夜のななふし-03(3)|楢﨑古都 @kujiranoutauuta #note #熟成下書き https://t.co/Ij8AG3asoH
— ✿すいすい✿ (@kujiranoutauuta) 2020年1月2日
ハルキを幼稚園へ送ると、私にはすることがなくなってしまう。バイトをする気にもならないし、金なら親父の不動産から毎月自動的に振り込まれてくる。
親父がいる部屋に戻る気はしなかった。かといって他に行くあてがあるわけでもない。電車に乗って歓楽街まで出てゆく気力もなかった。さしたる目的もなく、私は高校行きのバスに乗っていた。
駅とは逆方面へ向かうバスは、まだ遅い朝の通勤時ということもあって、まばらに人がつり革を握って立っていた。しばらくして空いた、センターライン側の席に腰を下ろす。みだれてしわくちゃになったセーラー服のプリーツを、両手で気持ち押さえつけながら座った。
視線を窓の外に投げ、気だるくバスに揺られた。信号待ちで停車しエンジンが切られると、少し効きすぎた暖房が車内にこもった。眺めていた右手の窓辺から、反対側の窓外に視線を変える。通路に立つ人たちの隙間をぬって、私は路地と人影に視線を取られた。車一台がやっと通れるくらいの狭い路地だった。三個の人影が、横たわるくたびれた猫を囲み覗き込んでいた。
しゃがみこんでいる中年女は、パーマのとれかかった髪を何度も耳にかける仕草をしながら猫の頭をなでていた。男が二人、女の後ろから様子を眺めている。白い寝巻き姿のまま表へ出てきてしまった寝癖の老人と、日がな散歩をして過ごしていそうな中年男だった。大の大人が三人も、薄汚れた一匹の猫を囲んでいる光景はいささか異様なものに映った。
猫は人に慣れているのか、なでられてもまったく微動だにしない。四肢を投げ出し、腹を見せて女のなすがままにまかせていた。男たちは揃って腕組みし、つっ立っている。
女が、赤ん坊の頭を持ち上げるときの要領で頭をそっと持ち上げたときも、猫はまったく動かなかった。ただ、見開かれた両眼が低い太陽に反射して金にも緑にもゆらいで見えただけだ。何ものも、それは見てはいなかった。女の手が猫の瞼を閉じる。待っていたかのように再びエンジンがかかり、バスは視線を引きずりながら走り出した。
目をつむり眠ろうとしても無理だった。まばたきするたび、瞼の裏に猫の姿がよみがえった。女の手に支えられた頭には重さがなかった。嫌なものを見てしまった、という後味の悪さはなかったが、心許ない不安定な所在なさは腕や足に滞っていた。効きすぎた暖房が疎ましく思えてきて、私はバスを降りた。
足が自然とさっきの路地へ向いた。ポケットから煙草を取り出し火をつける。かかとを削りながら歩いた。口元にあてた中指と人差し指を細めた目で追うと、北風に吹かれて煙が顔にかかった。
猫も人影もすでに路地にはなかった。冬の太陽が乾燥したアスファルトに弱い陽光を落とすばかりだった。ブロック塀の向こう側から、かすかに人の気配とテレビの音がする。猫に出会えなかった落胆よりも、安堵の方が大きかった。
ベルの音がして道をあけると、前と後ろとに幼い子どもを乗せた母親の自転車が走り抜けていった。無造作にひとつに束ねられた髪の毛が、子どもと一緒に揺れている。煙草を靴のかかとでもみ消して、両手をポケットにしまった。
路地を出て、私は陸橋を見つける。嬉々としてそれに向かい、登っていった。制服が汚れるのも気にせず、柵に足をかけ身を乗り出していた。腕や足に滞るものを、下から吹き付ける冷たい風で拭いたかった。車の走列に次から次へと自分を重ね合わせ、猫は轢かれて死んだのだろうかと考える。見下ろしていた顔を上げると、冬の晴天が高く広がっていた。
排気ガスの混じった冷気を胸いっぱいに吸い込み、勢いつけて柵から飛び退く。意味もなく笑い出しそうになるのをこらえて、階段を一段抜かしで下りていった。なぜハルキがジャングルジムに登りたがるのか、少し分かった気がした。